国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所のウェブサイトは2013年9月に移転しました。
新ウェブサイトはこちらからご覧いただけます。
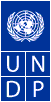
関連リンク検索 |
コソヴォ議会電子公文書(保管所) 支援プロジェクト (SPEAK)完了プロジェクト 2002年9月現在
背景コソヴォ紛争の恐らく最も消し去ることの出来ないイメージは、1999年の学校教育施設の広範囲で組織的な破壊であろう。紛争前の10年間は、教育分野の維持に対する必要最低限の投資しか無く、大規模な荒廃と放棄という結果を招いている。然しながら、すでにもろい状態だったコソヴォの教育システムを完全に不能にしてしまったのは、1999年の計画的な学校に照準をあてた破壊であった。教育基盤の2分の3以上(1200校)が破壊されたか、酷く被害を受け、殆どの備品、家具、物資などは略奪されたか、破壊された。 1999年以降、設備不足のために、生徒達は一日2,3シフトの中で学校教育を終了させている。多くの小学生達が、授業を受けるため、厳冬の危険なハイウェイを数キロも歩いて登校しなければならない。他にも、名目上は機能しているはずの設備も、公衆衛生や下水設備など生徒達を脅かす深刻な問題となっている。 教育・科学技術省(旧教育科学省―UNMIK条例2000/11により2000年3月に設立)は2001年11月の全域選挙後に設立され UNMIK条例2001/19 を踏まえている。同省はコソヴォの教育分野の戦略的プランとして「コソヴォ計画的教育システム」(DESK)を練りだした。 その目的は(1)現在進行中の民主的選挙と信頼できる政府への過渡期に、早急な回復と継続的な学習を確かなものにする、また(2)20世紀における現代的なヨーロッパ社会の必要性を反映した教育システムの長期的な改造、変革をサポートする、ことである。 ユネスコ、国連教育科学文化機構(UNESCO)、ユニセフ、国連児童基金(UNICEF)、国内の教育専門家、建築家、エンジニアとの協議において、教育省は学校再建ガイドラインを開発した。このガイドラインはNGOやその他の機関に対し、UNMIK監視過程において採用されていた規範、標準、規格の開発を含んだ学校設計の領域に関するアドヴァイスを与える。従って、修理、拡張・改装、新築を含んだ全ての学校設備に関する建築は教育省による許可が必要となる。 1999年6月に紛争が終結してから、生徒達が学校へ戻ることが可能な環境を整えることにあらゆる努力が払われてきた。緊急の必要性は、インフラ、教師と彼らのトレーニング、教科書とカリキュラム、少数民族に関する問題、心理社会学関係、そして若者などにわたっている。2002年5月時点で、緊急の修復や再建を必要としていた学校設備の80%以上が完全に復興し正常に機能している。これらの努力に対する主な資金提供団体はEC人道援助局(ECHO)、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)そしてUNICEF である。 プロジェクト概要2002年5月に終了したUNDPによる介入は、コソヴォの中心に位置し、戦争による著しい被害を受けたマリシェボ市の若者のための学校再建の要求に取り組んだ。プロジェクトを担当したアドラ・ジャパンと共に、UNDPは1軒の高等学校の修復、別の高等学校と体育館、4軒の小学校の全面的な再建築を行った。合計で3,000名以上の生徒達が、彼らの世代では殆ど始めての、身近で、安全、衛生的かつ現代的な教育設備を利用している。 プロジェクト目的1. 学校の基礎的な状況改善、またそれによる教育の質の改善 本プロジェクトの復興活動は、家具の提供、衛生システムの確立、暖房システムの強化を含む。各学校の設計図の開発はUNMIK/DESKユニットによって推奨されているガイドラインに適応している。再建された学校はカリキュラムを再開させている為、より多くの生徒を収容し、クラスごとのシフトの数が減らされている。これにより、該当の学校で提供される教育の質が改善されている。 2. 生徒達にとってより安全な学習環境の設立 本プロジェクトの第二の目的は、生徒達にとってより安全な学習環境を設立したことである。この目的は2つの表題における訓練を通して達成された。a) 環境の健全性、そして b) 地雷意識教育、のトレーニングプログラムが教育課、UNICEF、およびプリシュチナにあるマイン・アクション・センターとの連携により開発され、現行の環境、衛生教育や地雷に関するプログラムとの統一化を図っている。トレーニングに加え、地域のボランティアや生徒達が、建設現場の環境的配慮や更生の為にガーデニングや清掃に参加する意識を高めている。建築作業と同時進行で、これらの教育プログラムが該当の学校や地域社会に、自分達の環境を清潔に保つ持続可能な構造や新しい学校の地域社会による「所有者」意識の高揚を引き合わせる結果となった。 プロジェクト対象校 学校の建築作業は、新しい設備に対する地域社会の責務とオーナーシップを強調する為に、地域社会と生徒達の少なからぬ参加を活用することによって実施された。環境、公衆衛生、地雷や予期せぬ兵器に対する自覚活動は、鍵となる参加の素子や防衛力を包含している。 UNDPは、持続可能な平和と開発の戦略的な基盤として、特に人間の安全保障やコソヴォの若者達のニーズの進展を考慮している。コソヴォの人口の50%を占めていることから、若い世代のニーズ開発に対応することはコソヴォの将来的な社会や経済の回復のための必須条件である。 パートナーシップSRKプロジェクトの骨組みを準備するに当たって、UNDPはプロジェクト実行パートナーであるアドラ・ジャパンと協議を行いながら、地元のニーズの見極め、教育省の要望と将来的な計画、ドイツ軍コソヴォ治安維持部隊(KFOR)の協力の包括などを進めた。重要なことは、プロジェクト実行現場と運営上の骨子は、十分な地域社会と地方行政の関わりや業者間の協調抜きでは成し得ないという事である。 本プロジェクトは、日本政府拠出の「国連人間の安全保障基金」を用いて実施され、総費用260万米ドル以上が費やされている。 持続可能性地域社会の参加要素を含むことは、新しい学校施設が地域の必要不可欠な中心となり、メンテナンスの必要性に注意が払われること、を確かなものにする為の有利な投資である。地域社会の信頼の上に成り立つ、身近で安全、衛生的かつ機能的な教育設備は、コソヴォの未来を担う世代が人間の安全保障に関する十分な満足感を持てるようになるための基盤である。新しい設備が、コソヴォの持続可能な教育システムの構成要素となることを確かなものにするために、行政とUNMIKによる全てのしかるべき認可や規制が、本プロジェクト実行期間中に適用された。 現状SRKプロジェクトは2002年5月に完了し、マリシェボ市の学校教育環境を格段に進歩させた。小学校4箇所、高等学校2箇所と体育館の建設によりSRKプロジェクトは3500名以上の生徒達への支援を達成した。 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||